毎年秋になると、なんだか目が充血してかゆい!
そんな方はいませんか?
あなたがお困りのその症状は、もしかしたら花粉症かもしれません。
花粉症の季節といえば、春を思い浮かべる方が多いと思いますが、秋にも花粉症で悩まれている方は結構いるんです。
目の充血の原因になっているかもしれない、秋の花粉症についてお伝えしていきたいと思います。
<その他の秋の健康はこちら>
秋の健康管理、季節の変わり目や花粉症、食欲の秋の肥満対策も
秋の花粉症

春と秋の両方の季節に共通する花粉症の症状が、いくつかあります。
くしゃみや鼻づまり、サラサラした鼻水、目の充血やかゆみ、肌のかゆみ、熱っぽさなどです。
毎年のように秋になると目、鼻、のど、気管に不調が出て、その症状が長く続くといった場合、それは花粉症が原因かもしれません。
花粉症の人のうち、約15%が秋に症状が見られます。
私の周りでも花粉症の人は結構多いですが、春と秋の両方に症状が出るので、対策をしているという方もいますね。
秋の花粉症は秋の植物によるもので、夏の終わり頃から10月にかけて目や鼻の症状が出ます。
原因となる植物の種類もいろいろとあり、原因となる植物によってその症状も、若干変わることがあります。
また、スギ花粉症がある人では、秋の花粉症も発症しやすくなるといわれています。
秋の花粉症と間違えやすいのが、秋に増えるハウスダストのアレルギー症状と、季節の変わり目による風邪症状です。
植物の花粉に触れる外ではなく、家の中で症状が強くなるような場合は、ハウスダストの可能性もあります。
夏の高温多湿の好条件で大繁殖するダニは、秋になると死んでしまいますが、その大量の死骸がアレルギー症状を引き起こす原因になります。
衣替えで久しぶりに出す衣類や布団も、その温床になっている場合があります。
家の中で症状が起こる場合は、花粉症ではない可能性があるので、部屋の掃除を徹底的に行う、衣類や布団の洗濯をするなど、ハウスダスの対策をしてみましょう。
そして秋は季節の変わり目で、体調を崩しやすくなるため、風邪とも間違えやすい季節です。
目の充血は比較的花粉症と分かりやすいですが、他の症状の場合は「風邪かな?」と思うかもしれません。
熱もないのに症状が続く、毎年同じような時期に症状が長く続くというときには、それは花粉症かもしれません。
風邪と花粉症では、治療がまったく異なります。
症状から風邪と自己判断せず、病院で診察を受けるようにしましょう。
秋の花粉の飛散状況は?

花粉症に関係する植物の、花粉が飛散する期間は、大体8月から10月です。
飛散量のピークは9月で、10月になると落ち着き始め、11月になるとほぼ終了です。
春のスギやヒノキの花粉情報については天気予報でも発信されていますが、秋の花粉情報は発信されていないため、秋の花粉症についてはそれほど知られていないかもしれませんね。
秋の花粉症の原因として多いのは、ブタクサなどの雑草の花粉です。
スギやヒノキのような樹木の花粉とは違って遠くまで飛ぶということはなく、飛距離は数メートル程度になります。
近づかなければ花粉を浴びる確率は低くなるので、春の花粉よりは防ぎやすいともいえます。
秋の花粉の種類は?
秋の花粉症の原因として多い、代表的な植物についてお伝えします。
ブタクサ
よ~くよ~く見てごらん🎵花がビッシリ😃花粉症の原因とも言われているブタクサ😃 pic.twitter.com/FRYy4Xv3uJ
— チエウサ (@whitechieusa) September 25, 2019
キク科の外来種で、道端や畑、河川敷など生活圏に広く分布しています。
花粉の飛散時期のピークは10月で、関東では12月まで飛散することもあります。
ブタクサの花粉症はスギ、ヒノキに次いで3番目に多く、秋の花粉症の原因では最多になります。
1961年に日本で最初に報告された花粉症はスギではなく、このブタクサでした。
花粉症としての歴史も長く、秋の花粉症といえば多くの場合このブタクサになります。
ブタクサの花粉は午前中に飛散します。
花粉の粒子が小さく、気管支にまで入ってくると喘息のような症状を起こすこともあるので、鼻炎症状に加え、喘息のような咳症状にも注意が必要となります。
また、ブタクサの花粉はメロン、スイカ、キュウリなどウリ科の食物のアレルゲンと構造が類似していて、口腔アレルギー症候群を引き起こす可能性もあります。
秋に鮮やかな黄色い花を付ける、ブタクサと似ている外来種のセイタカアワダチソウと間違えている人も多いですが、葉と枝の伸び方が違います。
セイタカアワダチソウ
キク科、北米原産毎年 秋に
空き地、河原、土手に群生し
草丈1〜2.5mの茎先に
黄色い小花が
三角錐の形に集まり咲く繁殖力旺盛で
種子と長い地下茎で増え
他の植物の生育を妨げる
成分を根から出す花言葉は
「元気、生命力」
ご安全に良い一日を🍀#花言葉 #私の花世界 pic.twitter.com/AwwhIR5ClD— さくら餅子 (@sakuraricecake) November 5, 2018
セイタカアワダチソウは「虫媒花」(蜂などが移動することで受粉する花)で、花粉を飛ばす種類の植物ではないので、花粉症とは関係ありません。
ヨモギ
喉がイガイガするのは秋花粉のせいかしらん?
ヨモギが咲きだした。
ハイイロセダカモクメの幼虫とかおらんかな? pic.twitter.com/GA4gAjJhSb— Acleris(あくれりす) (@Acleris) September 22, 2019
日本では草餅や草団子に使われ、親しまれてきたヨモギです。
キク科の多年草で繁殖力が強く、道端や公園、堤防など生活圏に広く分布しています。
実はヨモギ自体は野草の中でも「和製のハーブ」「ハーブの女王」とも呼ばれるほど万能で、昔から身近な薬草として利用されてきました。
9月下旬に淡褐色の小さな花をたくさんつけるため、この花粉が花粉症の人にとっては影響をもたらしてしまいます。
ヨモギ花粉症も、鼻炎症状や喘息症状に加えて、ニンジンやセロリなどを食べる際には口腔アレルギー症候群の症状に注意が必要となります。
カナムグラ
9月22日、軽井沢雲場池。おだやかな休日の朝。薄雲の隙間から日差しが出ています。遊歩道脇でカナムグラが花(雌花)を咲かせていました。オオブタクサやヨモギなどと合わせて秋の花粉症の季節が始まっています。 pic.twitter.com/br7v7QAz0n
— 軽井沢草花館 (@kusabanakan) September 21, 2019
アサ科の植物で非常に繁殖力が強く、駆除するのが大変な事で知られています。
一年草ですが、爆発的な速さで広がっていき、あっという間に辺り一面を覆いつくします。
茎や葉柄には下向きのとげがあり、ほかの木や草にからみつきます。
野原や道端などに広く生息している一方、住宅地やオフィス街にも自生していて、電柱やガードレール等に絡みついて高い場所にも葉を付ける事があります。
カナムグラ花粉症も鼻炎・喘息症状に加え、口腔アレルギー症候群の症状に注意が必要です。
カナムグラ pic.twitter.com/TD0VM3o6Tu
— 季節の花々 (@shimura_flowers) September 23, 2019
日常生活でできる対策法
秋の花粉症対策も、できるだけ花粉を浴びないようにすることが基本です。
秋の花粉は樹木ではなく雑草がほとんどなので、普段通る道に秋の花粉症の原因になる植物がないかをチェックし、たくさん生えている空き地などにはできるだけ近づかないようにしましょう。
これらの植物は自宅の庭にも雑草として生えることがあるので、葉の形状などを記憶しておき、花が咲く前に除草するよう心がけましょう。
秋の花粉症に対しても、その対策は春と同じです。
マスクや花粉症用メガネの着用、花粉の付着しにくい素材の服を着る、帰宅時には玄関前で花粉をはらう、帰宅後の洗顔やうがい、掃除の徹底、空気清浄機の利用などの対策が有効です。
まとめ
秋は花粉症、ハウスダスト、風邪と何かと体調を崩しやすい季節です。
自分の症状が一体何の原因からきているのかをしっかりと見極め、早めの適切な対応を行っていきたいですね。















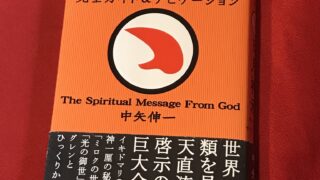








コメント