私たちは、普段何気なく言葉を使っています。
その言葉が、子育てでは子どもたちに大きな影響力があることを知っていますか?
親が毎日使う言葉は、子供の性格や人格形成、そしてその子の人生にも大きく影響しています。
今回は、子育てする上で重要な影響力を持つ言葉、特に親が日頃使う言葉について、お伝えしていきたいと思います。
<その他の子育てについてはこちら>
子育てのポイントやコツをおさえて親子で幸せな子育てを
親の言葉が子供の自己肯定感に影響する

子供は、育った家庭環境の影響を大きく受けます。
その家庭環境の中には、親が日常的に使う言葉も含まれています。
子供は年齢が小さいほど、潜在意識の扉の右脳が開いていて、毎日かけられる言葉がその潜在意識の中に、どんどん入っていきます。
それはやがて、その子供の性格や人格形成にも影響します。
その子がまだ小さくて、自分ではうまく話せない年齢だとしても、それは話すことができないだけです。
親が話す言葉の意味は理解していたり、親の気持ちや言葉の意味を、雰囲気や表情などから敏感に感じ取っています。
子供は自分という存在を受け入れ、認めてもらう体験を積み重ねていく中で、自己肯定感を高めていきます。
この自己肯定感は自尊心、自己重要感などとも言われ、人間としてとても大切なものです。
自己肯定感が低いと、やがて大きくなって自分の人生を思うように自由に生きられる年齢になってっからも、自分の人生に対して積極的に生きることができなくなります。
小さい頃から、一番身近で影響力のある親が、子供を認める言葉がけを日々心がけましょう。
おすすめの自己肯定感を高める言葉

お子さんがもし就学前で、ある程度まだ小さいのなら、おすすめしたい言葉があります。
それは「生まれてくれてありがとう。」「大好きだよ。」「生まれてくれてママは幸せ!」という言葉です。
シチュエーションによって、伝え方はいろいろバリエーションがあっても良いと思います。
これらの言葉を繰り返しかけられることで、自分は生まれてきて感謝され喜ばれる存在なんだと、自分の存在が無条件に価値のあるものだということをインプットすることができます。
何ができるから価値がある、という条件付きではなく、生まれてきたこと、存在自体に価値があるのです。
私は実際に、自分の子育てで実践し、子どもたちが小さい頃から、繰り返し伝えてきました。
また、相談のあった保護者には、自分の実践してきたことをお伝えしてきたりもしました。
うちの子供たちにとっては既に「そんなこと、とっくに分かってるよ!」「どうせ僕のこと好きなんでしょ!^^」とこたえるくらい、当たり前のことになっています。
繰り返し実践し続けることで、子どもたちの潜在意識の中に、しっかりインプットすることができたと思っています。
自己肯定感は発達の土台になる部分
保育士をしてきて、自己肯定感が低いお子さんや、親との愛着形成がうまくできていないお子さんと出会うことがたびたびあります。
自己肯定感のしっかりとした土台がなければ、その上には、いくら周りが頑張って働きかけをして何かを乗せようと思っても、なかなか積み上がってはいきません。
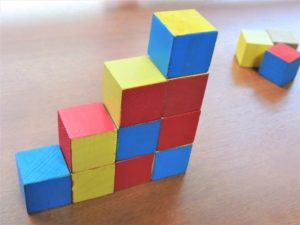
自己肯定感や愛着形成というのは、発達の上での大切な土台になる部分なのです。
右脳教育や潜在意識など様々なことを学んできて、私がたどり着いた子供の自己肯定感を高める効果的な言葉が、先ほどの「生まれてくれてありがとう。」「大好きだよ。」「生まれてくれてママは幸せ!」です。
子供がある程度大きくなってきてから突然始めたのでは、言う親も言われる子供も、照れくさかったりなかなか実践しにくいと思います。
なので、この言葉がけは、ある程度小さいお子さんの場合におすすめです。
子供のやる気を引き出す言葉

子供の年齢が小さいうちに、自分は大切な存在だという自己肯定感をしっかり高めていきます。
それができてきたら、次は年齢が上がるごとに、子供なりに自分の世界を少しずつ広げながら、様々なことにチャレンジしていってほしいですよね。
子供も大人も、自分が興味を持ったことを積極的に体験してみるということが、人生においては大切です。
そのやる気を引き出す言葉は、やはりポジティブで前向きな言葉になります。
これは当たり前のように思いますよね。
でも、毎日の生活の中で、実際にこれができていますか?
子供がやろうとしていること、やりたいと思っていることに対して、「できない、無理、難しい」と思うのは、親が親の価値観で思っているだけです。
今の子供たちは、私たち親世代よりももっと軽やかにチャレンジでき、乗り越えていく力があります。
また、失敗に対しても失敗とは受け止めなかったり、全く気にすることがなかったり、受け止め方も軽やかです。
親の価値観で決めつけず、後押しする言葉をかけましょう。
子供も大きくなればなるほど、様々な出来事を経験していきます。
その中で、親から日常的に否定的な言葉をかけられると、少しずつ「自分はどうせ何をやってもだめなんだ」と、いろんなことに対してのやる気や自信を失っていきます。
失ったやる気を引き出すのは、なかなか大変なことです。
子供へは否定的な言葉は控え、前向き、肯定的な言葉を心がけましょう。
子供にとって良い言葉を親がまず使う

お子さんが小さいほど、親の習慣や言動を、それが当たり前のものとして、そのまま自分の中に取り込んでいきます。
子供には良い習慣を身につけてほしいですよね。
私の実践の中で、子供が小学生になった時に、良い習慣として身についたと感じたことがいくつかあります。
そのご家庭によってできる、できないはあると思うので、あくまでも我が家の場合ということで参考までにお読みになってくださいね。
正しい日本語や敬語
まず一つ目は、正しい日本語や敬語です。
これは私たち夫婦が、いつも敬語ということはもちろんないのですが、夫婦間の会話も、たびたび敬語が入ります。
特に相手に何かして欲しいこと、お願いしたいこと、お使い立てがある時には、お互い大体敬語です。
「ちょっと〇〇していただけますか?」
「それいただいでもいいですか?」
「お願いできますか?」
などです。
決して夫婦仲が悪い訳ではないですよ^^
すると、それが我が家の当たり前になっているので、子供たちも敬語が上手です。
「ちょっとこれ、僕いただいちゃうね」
「今度のお休みに、○○したいです」
など普通に言います。
返事は「はい」
それから二つ目は、敬語にも通じますが、返事をするときに親である私たちもよく「はい」と返事をします。
子供たちに何か言われた時にも、分かった時には普通に「はい」と返事をします。
すると子供たちも、親に何か言われた時に、素直に「はい」と返事をするのが当たり前に育ちました。
子供たちに何か声をかけた時に素直な「はい」という返事が返ってくるのは、親としても嬉しいし心地よいものですよね。
間違えたら謝る
そして最後の三つ目は、親も間違えたことをしたと思ったら、そのままにせず必ず謝るということです。
その時はイライラしてしまって謝れなかったとしたら、少し時間をおいて落ち着いてから「さっきはごめんね」と謝ります。
子供たちも間違えた、悪いことをしたと思うとすぐに謝ったり、その時には言えなくても「さっきは〇〇してごめんなさい」が言える子になりました。
我が家の子育てする上で取り組んだことで、子供にとって良い習慣になった、3つのことをお伝えしました。
①敬語
②「はい」という返事
③間違えたことは必ず謝る
の3つです。
家庭環境や親、夫婦間のそれまでの習慣にも左右されるので、なかなか取り入れるのは難しいとは思います。
でも、このことから何を言いたいかというと、親の日々使っている言葉が、思っている以上に子供に影響するということです。
保育士をしている中でも、子供が親の口調そっくりというご家庭も、たくさん見てきました。
子供にとって良い言葉とは何か、子供にどんな言葉で話す人に育ってほしいかを考え、自分たちの言葉を少し振り返ってみるのも大切ですね。
まとめ
今回は「子供のやる気を自然と引き出す親の言葉がけの重要性とは」ということでお伝えしてきました。
親が使う言葉は、子供の自己肯定感ややる気、日々使う言葉にも影響を与えます。
今回お伝えした内容は、年齢が小さい子供ほど取り入れやすく、効果が高いと思います。
でも大きくなってからでも、親が使う言葉や子供にかける言葉を良いものにかえることで、子供に良い影響を及ぼすことができます。
ぜひ参考になさって、ご家庭に合った形にアレンジしながら取り入れてみてくださいね!











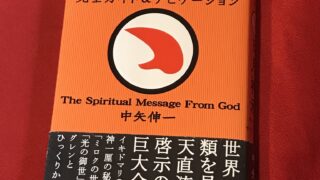












コメント